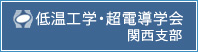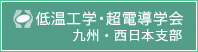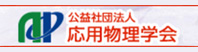2025年度 総会
2025年度東北・北海道支部総会が,2025年4月18日(金)に対面形式で開催され,総会後,記念講演会・事業会員企業の紹介,学生研究交流会の紹介が開催された。概要は以下の通りである。|
1. 東北・北海道支部総会 14:00〜15:00 |
||||
場 所 |
: | 東北大学金属材料研究所 本多記念館 3階 会議室(旧視聴覚室) |
||
|---|---|---|---|---|
| 伊藤庶務幹事より,総会員数68名に対し,総会出席者数15名,委任状数19通の合計34名が支部規約の定足数(会員の1/4以上)を満たしており,総会が成立した旨の宣言の後,議長に津田理氏(東北大)を選出した。 淡路支部長挨拶の後,以下の議事について審議した。 | ||||
(1) |
令和6年度の活動報告がなされた。 | |||
(2) |
令和6年度の決算報告及び会計監査報告がなされた。 | |||
(3) |
令和7年度の支部役員案が諮られ承認された。 | |||
(4) |
令和7年度の活動計画案が諮られ承認された。 | |||
(5) |
令和7年度の予算案が諮られ承認された。 | |||
| 令和7年度に計画されている主な活動計画は,令和7年9月1日~3日に開催予定の「超伝導物理の基礎と,超伝導工学の基礎を直感的に理解する。」をテーマとした若手セミナー,令和7年9月および12月に開催予定の学生研究交流会(9月:オンライン交流会,12月:対面交流会),令和7年10月30日に東北大学で開催予定の東北・北海道支部30周年記念事業(特別記念講演会および祝賀会),令和7年11月22日に仙台市で開催予定の「超電導リニア」をテーマとした市民講演会,令和7年12月4日~5日に山形市で開催予定の応用物理学会東北支部との共催による学術講演会,令和7年4月18日,11月22日,令和8年3月2日に開催予定の役員会である。 | ||||
|
2. 記念講演会 15:00~16:20 |
||||
場 所 |
: | 東北大学金属材料研究所 本多記念館 3階 会議室(旧視聴覚室) |
||
|---|---|---|---|---|
参加者 |
: | 24名 |
||
題 目 |
: | 「超電導線材の特性を活かすコイル化技術とその応用」 |
||
講演者 |
: | 石山敦士氏(早稲田大学教授) |
||
| 今年度の記念講演会では,早稲田大学石山敦士教授から,「超電導線材の特性を活かすコイル化技術とその応用」という題目でご講演をいただいた。石山先生がこれまで取り組まれてきた研究内容を中心に,コイル設計技術,コイル化のための基盤技術,REBCOコイルの応用例について,幅広くご紹介いただいた。 導入では,超電導コイルの社会実装にあたって2つの障壁として,①超伝導材固有の常電導転移事故に対するコイル保護,②高い製造コスト,があり,超電導線材の特性を最大限に活かしつつこれらを乗り越える必要がある,という基本的な考え方をお話いただいた。そのためのコイル設計技術としては,まず,設計要求仕様(発生する磁場,向き,均一度,空間の大きさ)を考え,その際にどのような電磁的特性,熱的特性,機械的特性を満たす必要があり,さらに安定化と保護が実現できるか,といった観点での最適化設計が必要である。また,合理的な設計法として,超電導線材の特性による制約条件の他,製作段階で発生する設計とのずれや設計モデルの影響(線材形状など)を踏まえ,目的関数として巻線重量(体積)を最小化することを考える必要がある,とのことであった。石山先生は1988年に電磁界と最適化手法の世界初の論文を,さらに1996年には,遺伝的アルゴリズムとシミュレーティド・アニーリングを組み合わせたコイルシステム最適化の論文を公開されている。1980年代後半から計算機援用数値解析の最適化が主題となっていたが,近い将来には生成AIがこの分野でも導入され,使用目的・要求仕様を入力することで答えが得られる環境ができるだろうとの見解を示された。 コイル化のための基盤技術のセクションでは,REBCO線材がコイルとして使えれば未踏ステージでの応用が期待されるが,線材がテープ状でコイル化しづらい特徴があるため,線材化技術だけでなくコイル化技術が重要であることをまずお話された。また石山先生が提唱された「5-H (High):高機械強度・高電流密度・高安定・高磁場・高精度磁場」がREBCOコイル基盤技術として重要であり,二律背反の関係がある高電流密度と高安定(熱的安定性)を両立する「無絶縁コイル」,高機械強度により高磁場を実現する「Yoroiコイル」,不斉磁場の発生源である遮蔽電流を解析する「高速多重極法(FMM)」に基づく高精度磁場達成手法,について順を追って説明していただいた。さらにREBCOコイルの応用例として,石山先生が開発に取り組まれてきた多くの事例の中から,MRIとスケルトンサイクロトロンの開発についてのご紹介をいただいた。 講演の最後には,安河内昴先生の1974年の低温工学サロン記事「BEBC超電導マグネットの故障」を引用され,失敗を重ね,その失敗を公表し,共有していくことが革新的技術を手に入れるために重要である,とのメッセージを石山先生からいただいた。質疑応答の際にも,失敗を公表できる雰囲気を醸成していくことが重要である,と賛同する声が参加者からあり,非常に盛り上がりのある講演会となった。学生会員からも数値解析手法や二律背反があるテーマでの考え方など多くの質問があり,石山先生から丁寧な回答をいただき,初学者にとってもわかりやすく学びの多い内容であった。 | ||||
 |
|
|---|---|
記念講演会(石山先生のご講演)の様子 |
|
3. 事業会員企業の紹介 16:20~16:40 |
||||
場 所 |
: | 東北大学金属材料研究所 本多記念館 3階 会議室(旧視聴覚室) |
||
|---|---|---|---|---|
紹介者 |
: | 淡路 智氏(東北大学) |
||
参加者 |
: | 20名 |
||
| 東北・北海道支部の事業会員企業を支部長から支部会員に紹介する機会を本年度新たに設けた。本紹介では,会場スクリーンに各事業会員企業のウェブサイトを投影し,特に低温工学・超電導学会の研究分野に関する事業・販売製品に関しての紹介を行った。また,同席していただいた事業会員企業の出席者からご挨拶をいただき,会場にて名刺交換を行う機会を設けた。今後も事業会員企業に東北・北海道支部へのご協力をお願いするとともに,支部会員と事業会員企業の交流を促進できるような試みを続けていくことを考えている。 | ||||
|
4. 学生研究交流会の紹介 16:40~17:00 |
||||
場 所 |
: | 東北大学金属材料研究所 本多記念館 3階 会議室(旧視聴覚室) |
||
|---|---|---|---|---|
紹介者 |
: | 野島渉平氏(東北大学) |
||
参加者 |
: | 20名 |
||
| 東北・北海道支部の会員や東北・北海道地区の学生に周知することを目的に、本年度で6期目となる「学生研究交流会」の活動内容の紹介を実施した。本交流会の2025年度代表である野島渉平氏(東北大学博士課程学生)から学生研究交流会の発足の経緯,これまでの活動実績,今後の活動予定などが紹介された。本組織は全国の低温工学・超電導に関係,関心のある学生(高専生~博士学生で低温工学・超電導学会の会員/非会員は問わない)同士の交流を促進することを目的に,コロナ禍をきっかけにして東北・北海道支部の各大学に所属する学生が自発的に設立したものであり,同支部の支援を受けて活動を継続している。これまでに約100名の学生が参加し,昨年度開催したオンライン交流会でも全国から8研究室16名の学生が参加した。一昨年度までは研究をメインにおいた交流(ポスター交流,講師による講演会)としていたが,昨年度は自己/研究室紹介,小グループに分かれての交流(10分×4サイクル)とし,研究を始めたばかりの学部4年生や修士1年生にも参加しやすいようなプログラムとした。アンケート結果でも他学生との交流ができた,交流会に満足した,と参加者全員が回答し,今後の学会では円滑なコミュニケーションが取れそう,研究のモチベーションが増えた,といった感想があったと報告された。本年度は,従来のオンライン交流会を9月頃に開催することを予定しており,さらに基盤強化委員会・若手の会と連携し,秋季低温工学・超電導学会の機会を利用した対面交流会も企画しているとのことであった。 | ||||
|
5. 懇親会 17:30~19:30 |
||||
場 所 |
: | 東北大学金属材料研究所 強磁場超伝導材料研究センター 会議室 |
||
|---|---|---|---|---|
参加者 |
: | 17名 |
||
| 記念講演者の石山敦士氏を交えて恒例の懇親会を開催し、支部会員の親睦を深めた。 | ||||
(東北大学 淡路 智,伊藤 悟)